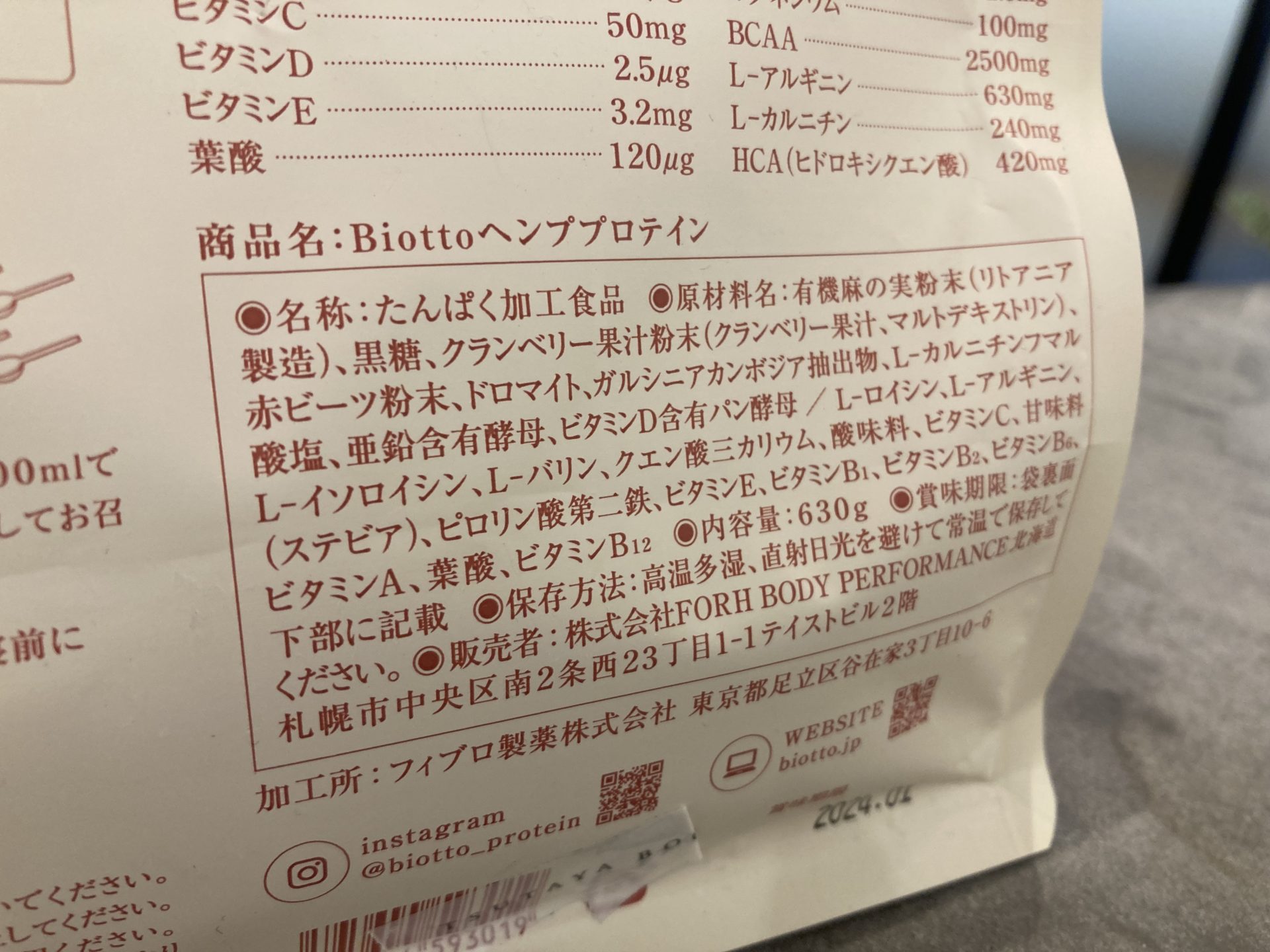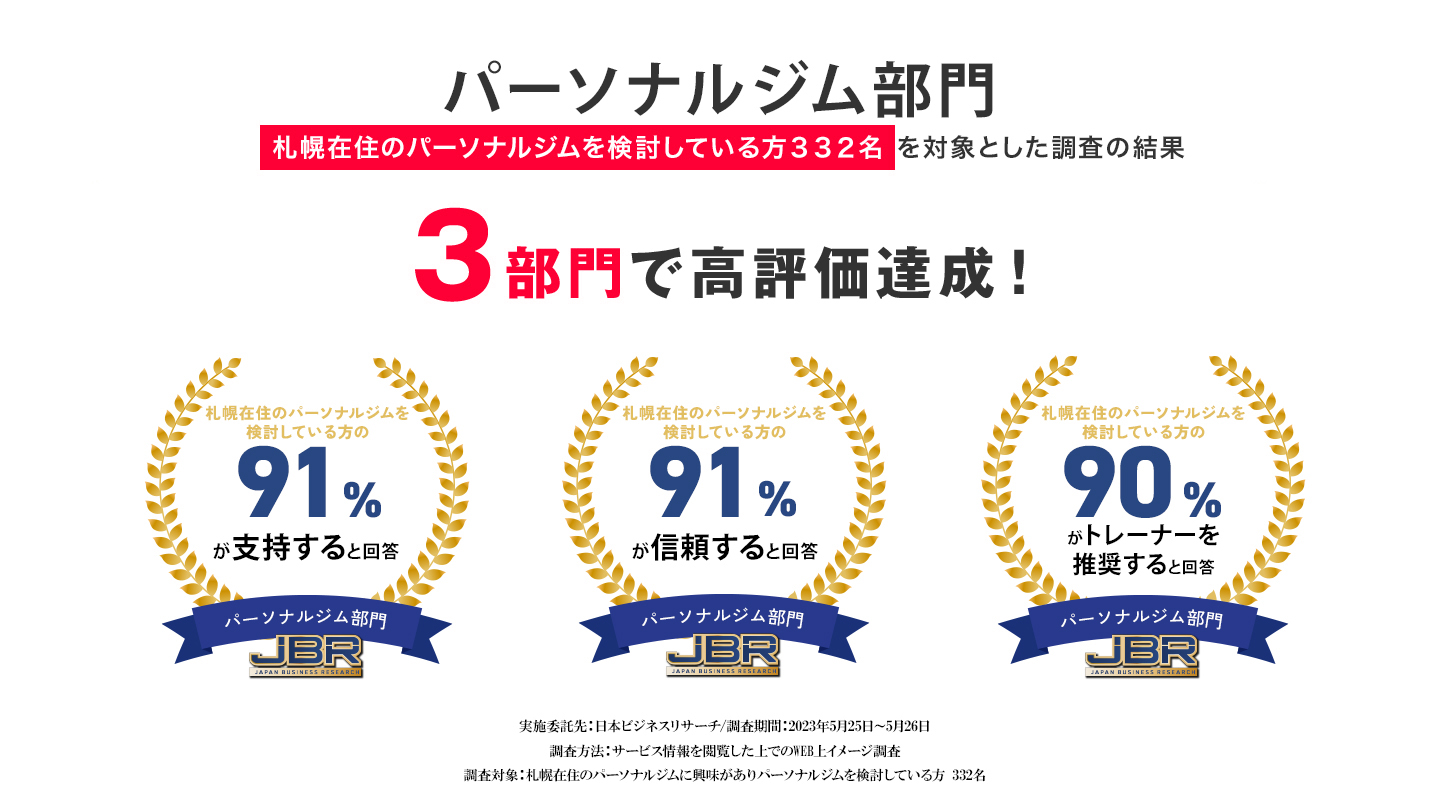『内臓脂肪』を落とす3つの方法
全国調査では年末年始に太ってしまう方が75.3%、平均2.04kgとの調査結果が出ている通りあなたもその一人ではないでしょうか?どうしても食生活が乱れ、エンプティカロリーになり正月太りになりますよね。
さて、今回はそんな太りやすいこの時期に少しでも早くリカバリーし特に身体に不必要な内臓脂肪の落とし方を3つご紹介します。

目次
内臓脂肪の落とし方①:朝食は抜くな。
内臓脂肪の落とし方②:魚を増やし、肉脂を減らせ。
内臓脂肪の落とし方③:食物繊維を味方にせよ。
朝食は抜くな。
食事を減らせば体重なんてすぐに減ります。しかも炭水化物を抜いた糖質制限系は水分量が先に減るため2.3kgの減量は比較的早く進みます。デメリットとして筋肉量も同時に減ってしまうため注意が必要です。
基礎代謝も今なら家庭用の体重計で測定できると思います。基礎代謝は1日に何もしなくても勝手に消費していくれるカロリーですが、例えば1500kcalの基礎代謝を持っていたところ体重が落ち筋肉量も落ち1450kcalになったとします。
マイナス50kcalです。1ヶ月で1500kcalになります。6ヶ月で9000kcal=脂肪1kgに相当します。歳を取れば筋肉量が徐々に減っていきますが食事量が変わらなければ筋肉量は減り、体脂肪が徐々に増えていくことになります。若い時のように痩せないのはこのためです。さらには活動量も減っていきますので歳をとって減量するには運動量も上げていかなくてはならないため時間が必要となるわけです。全く、困ったものです。そうならない予防を普段から習慣化させていくことが本質的ですが、内臓脂肪が高い人の共通点に朝食を取らない方が多い傾向にあります。
まず起床後、交感神経にスイッチが入ります。太陽の光と朝食がそれをONにしてくれます。脳とカラダのリズムを合わせます。朝食を抜くと脳とカラダのリズムが合わないため代謝が上がらない状態(内臓脂肪のエネルギー消費が減る)で1日をスタートすることになります。ガソリンがほとんど入っていない状態でドライブに出発する車のようです。
そして、お昼にご飯を食べると一気に血糖値が上がって脂肪は合成されやすくなりますます太りやすくなります。昼も控えめで夜ドカ食い&遅い時間に食べれば消化吸収が滞り翌日のまた朝ごはんは食べれない。この悪のスパイラルをやめなくてはなりません。なので、まずは朝食を取りましょう。

朝なかなか食べれない方はギリシャヨーグルトにはちみつをかけて食べるのがオススメです。またはヨーグルトを朝食べるだけでも変わりますのでまず、やってみましょう。
魚を増やし、肉脂を減らせ。
身体の余分な脂肪を落とすのだから、真っ先にカットしたい油脂。
例えば、豚ロース肉の脂やバラ肉のようなあの白い脂、鶏肉の皮、マヨネーズや揚げ物など。まずはこれらを積極的に取らないようにしたい。また、脂肪と糖質の組み合わせで代表的なチャーハンや、焼きそばなどあなたがよく知っている高カロリー食をセーブする必要があります。

これらの脂はカットしたいですが、カラダの生命に必要な脂があります。それは「多価不飽和脂肪酸」
オメガ6系脂肪酸(植物油)とオメガ3系脂肪酸(エゴマ油、亜麻仁油)に含まれるαリノレン酸、魚の油(DHA、EPA)の脂肪酸のことです。
このオメガ3系は脂肪燃焼効果、コレステロール値の改善、生活習慣の予防として機能します。
食物繊維を味方にせよ。
内臓脂肪はほとんど、腸間膜にたまる。つまり消化管全体を刺激して腸の働きを促せば、余分な脂肪もつきにくい。カラダを温めるのも効果的。腸を働かせるといえば食物繊維を積極的に取ることです。
野菜だけではなく、海藻、きのこ、豆など食材をバランスよく取り入れましょう。普段から海藻やきのことってますか?

昆布やわかめ、大豆、パンならライ麦は水溶性食物繊維のため消化物をドロドロの状態にするため、滞留時間が長くなり小腸の動きが良くなります。
ごぼうや豆、きのこは不溶性食物繊維が豊富で便のカサを増やし、大腸の働きを良くしてくれます。

そのため、食物繊維の働きを活かすために細かく切らず、繊維にそって切り、野菜スティックのサラダにすると良いでしょう。
こんな食材を取る良いでしょう。ということでまとめると
普段朝食を食べれない方はヨーグルトから始める。
肉系から魚介類を積極的に取る。
刺身、鯖の塩焼き、ひじきの煮物やわかめと豆腐のお味噌汁、漬物、冷奴、お浸しなど。
なんだかんだ日本人の腸には日本食が合うのでこの年末年始に太ってしまった方は意識して食べ物を変えると良いでしょう。
あとは定期的な運動を続ければ、あなたの身体はいつも良い状態、コンディショニングができていると言えます。
まず実践。不安な方や一人ではなかなかできない方は一度、札幌円山のパーソナルトレーニング&コンディショニングジムFORHに相談してみてください。
お待ちしております。
最後までお読みいただきありがとうございました。